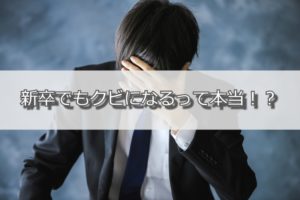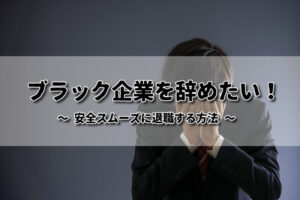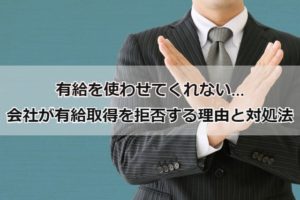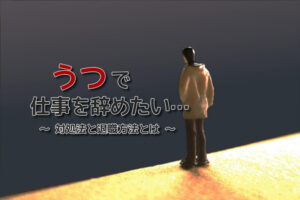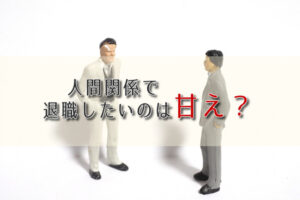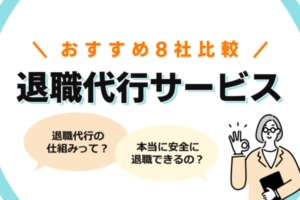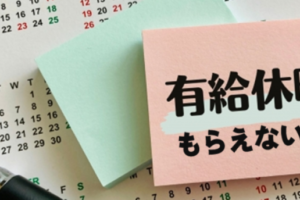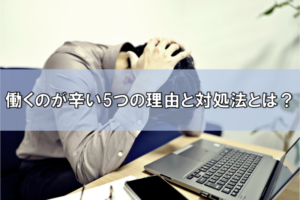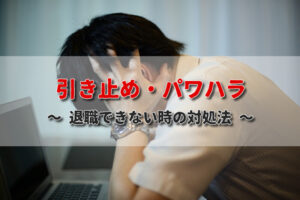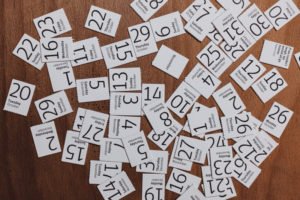労働基準監督署に相談したらどうなる?仕事で困った時の相談先と解決方法

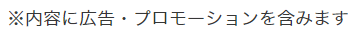
「労基に相談したら対応してもらえる?」
「労働基準監督署ってどんな場所?」
「労基」こと「労働基準監督署」。名称は知っていても「労働基準局」「労働局」との違いが分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では労働基準監督署の役割や労働基準局・労働局との違い、相談時の注意点について解説します。
職場の上司・同僚や企業との間でトラブルがあり、相談する先を探している方は必見です!

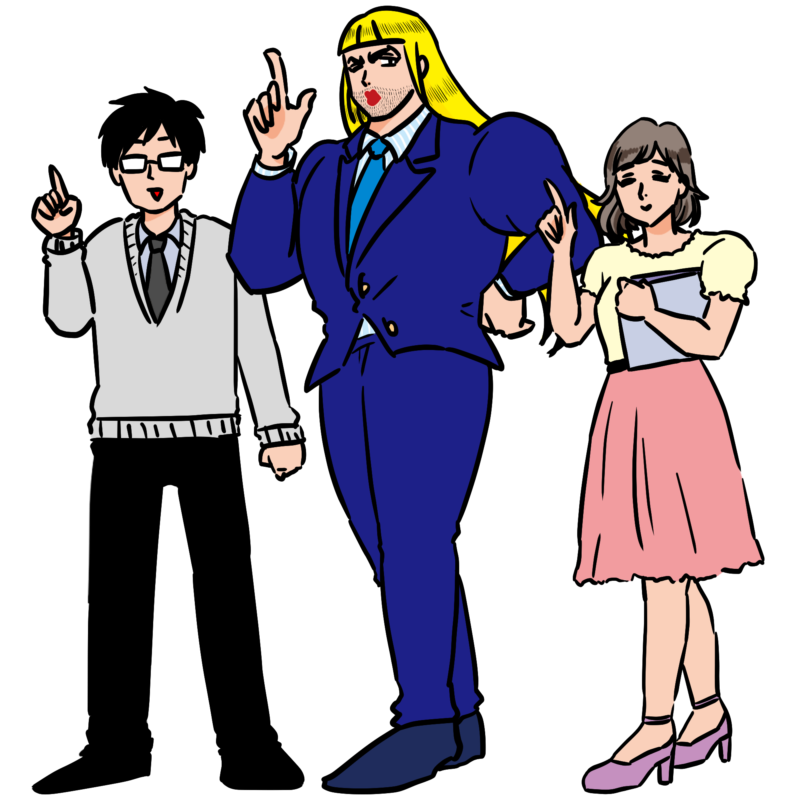
- ヒュープロは未経験でも利用できる?未経験者のヒュープロの口コミと活用法 2023/12/18
- ヒュープロは経理の転職でも使える?経理転職を成功させるヒュープロの活用法 2023/12/18
- Amazonブラックフライデーで何買う?2023冬のボーナス事情も調査 2023/11/17
目次
労働基準監督署/労働基準局/労働局の差
厚生労働省が管轄する「労働基準局」「労働局」「労働基準監督署」には上下関係があり、役割も異なります。
- ①厚生労働省
②労働基準局
③労働局
④労働基準監督署
労働基準局とは
労働基準局は厚生労働省の内部部局で、労働者が直接相談する機関ではありません。
厚生労働大臣が監督・指揮する「厚生労働省の中にある部局」として労働問題に関する事務を扱っています。
労働基準局は全国で一箇所にしかなく、各地にある労働局、労働基準監督署の指揮・監督をするのが役目です。
必要に応じて違反企業の調査立ち会いや、法令の施行をする機会もあるでしょう。
労働局とは
正式名称は都道府県労働局。一般的には「大阪労働局」や「東京労働局」と、都道府県名を付けて呼ばれています。
厚生労働省の地方支分部局として全都道府県に配置されているのが労働局です。
労働局には相談用窓口が設置されていますが、労働局の指導に法律的な強制力はありません。
法律に関する知識提供と解決への選択肢を提示するのが労働局の主な職務。
いじめやパワハラなどは男女雇用社会均等法に違反した行為で、労働基準監督署ではなく労働局の管轄となります。
● 解雇、雇い止め
● 配置転換、出向
● 昇進、昇格
● 労働条件の不利益変更
● セクハラ、パワハラ
● 労働契約に関する紛争
● 募集、採用に関する紛争
● 損害賠償(営業車の破損など)
参考:「都道府県労働局一覧」厚生労働省
労働基準監督署とは
労働基準法に則って全国の会社を監督する行政機関、「労働基準監督署」。
労働基準監督署は労働者の救済ではなく「違反企業の取り締まり」を目的としています。
不当解雇の相談をしても、労働基準法に反していると断定できないと動いてもらえません。
確実に「労働基準法違反」と示せる証拠(タイムカードや給与明細)を用意して相談に行くといいでしょう。
労働基準監督署に相談できる主な内容
- 賃金未払い(未払い残業、手当が出ないなど)
- 長時間残業や休日がとれない
- 労働者の安全が守られない危険な作業
- 雇用契約と労働条件が違う
- 勤めていた会社が急に倒産した
- 不当解雇
労働基準法に違反しているかの判断が難しいなら、訪問する前に電話で確認するか、都道府県労働局への相談がおすすめです。
署内に都道府県労働局の相談スペースが設けられている労働基準監督署もあるので、ホームページ等でチェックしましょう。
【労基?弁護士?】相談すべき場所まとめ
機関によって扱う問題は違うので、トラブルの内容に合わせた相談機関を利用しましょう。
| やりたい行動 | 相談先 |
|---|---|
| 相手を訴えたい | 法テラス・弁護士事務所 |
| 訴えずに解決したい/まずは相談したい | 都道府県労働局 |
| 労働基準法違反に対処してほしい | 労働基準監督署 |
| 今すぐ職場を辞めたい | 退職代行 |
専門家に相談&提訴→法テラス
法的な判断や効果のある手段について専門家に相談したいなら、法テラスに相談してみてください。
法テラスでは、トラブル内容に合わせた関係機関を案内してもらえます。
いじめ・パワハラ・解雇→都道府県労働局
職場でのいじめやパワハラが原因の解雇などは都道府県労働局へ相談しましょう。
社内に相談窓口や労働組合が存在しない方も、都道府県労働局なら受け付けてもらえます。
労働基準法の問題→労働基準監督署
賃金未払いや長時間残業など、労働基準法違反は労働基準監督署への報告ができます。
悪質な違反をしている証拠を用意しないとすぐに動いてもらえないので、準備は念入りにしておいて損はありません。
今すぐ辞めたい→退職代行
訴えるか訴えないかよりも今の職場を辞めたいなら、退職をスムーズに進められるサービスを利用しましょう。
弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスでは、職場への連絡に加えて残っている有給の取得や未払い給与の請求を依頼できます。
なるべく労力をかけず、トラブルを避けたい方は利用を検討してみてください。
弁護士の退職代行サービス
| 弁護士法人みやびの退職代行サービス | |
|---|---|
| 退職代行サービス | 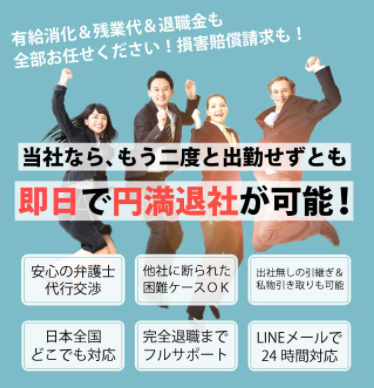 |
| 依頼費 | 55,000円 |
| 相談窓口 | メール LINE |
| 相談料 | 無料 |
| 特徴 | 日本全国対応 出社なしの引継ぎや私物引取り可能 他社に断られた困難ケースもOK メールLINE24時間対応 |
| 無料相談 |
労働組合の退職代行サービス
| 退職代行Jobs(ジョブズ) | 退職代行ニチロー | |
|---|---|---|
| 退職代行サービス |  |
 |
| 依頼費 | ■安心パックプラン 退職代行+労働組合 29,000円 ■シンプルプラン 退職代行 27,000円 |
一律28,000円 ※内、労務サポート費用3,000円は税込金額 |
| 相談窓口 | 電話 メール LINE |
LINE メール |
| 相談料 | 無料 | 無料 |
| 特徴 | 顧問弁護士監修 労働組合と連携 現金後払いOK 追加費用なし |
労働組合が運営 早朝・深夜24時間対応 アフターフォローも充実 |
| 無料相談 |
| 退職代行ガーディアン | |
|---|---|
| 退職代行サービス | 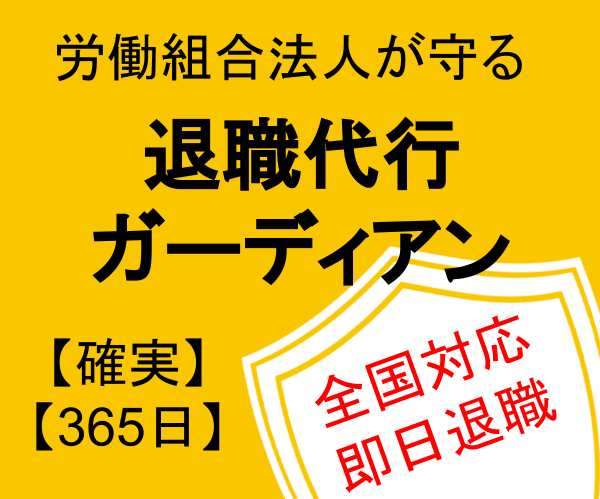 |
| 依頼費 | 一律29,800円 |
| 相談窓口 | 電話 LINE |
| 相談料 | 無料 |
| 特徴 | 東京都労働委員会認証の労働組合法人が運営 追加費用なし |
| 無料相談 |
労働基準監督署に相談したらどうなる?
2018年7月からは、一部の業務が民間に委託されています。
外部から雇われた臨時職員や法律の知識がない職員も窓口対応をしているので、その場で問題が解決するとは限りません。
参考:「労働監督の民間委託を決定 平成30年度、規制改革推進会議」産経ニュース
労働基準監法に明確に違反していれば対応が見込める
明らかに労働基準法違反をしている企業が相手なら、専門家による法律に則ったアドバイスや調査、是正勧告も期待できます。
機関の上下関係では一番下に位置する労働基準監督署ですが、持っている権限は強力です。
労働基準監督官の権限
労働基準監督署に所属する「労働基準監督官」は、「臨検監督」と「司法警察官」の権限を持っています。
- 臨検監督
- 立ち入り調査が出来る
- 司法警察官
- 逮捕や強制捜査ができる
労働基準監督官は強制捜査や立ち入り捜査をして違反企業の摘発を実施しますが、全ての事例に対応できるわけではありません。
年間約100万件もの相談に対し全国に配置されている労働基準監督官の人数はわずか3,000人程度と明らかな人手不足であり、どうしても人命に関わる問題が最優先されます。
労働基準法に違反していると断定できる証拠がなかったり、悪質ではないと判断されたりすると、対応は望めなくなります。
労働基準監督署への相談に必要な準備
年間100万件の相談に対し、全国に321署ある労働基準監督署に配置された労働基準監督官はわずか3000人程度。
全ての事例に関わるのは不可能なので、証拠が揃っていない相談は優先順位を下げられてしまうでしょう。
労働基準監督署に対処してもらいたいなら、事前に準備を整える必要があります。
相談前にできる準備
相談する前に、労働基準監督署で伝える情報の整理と関連する「証拠」を準備しておいてください。
すぐに動いてもらいたいなら、実名で「申告」するのもポイントとなります。
ハラスメントによる損害賠償請求など、個人との問題は労働基準監督署では解決できません。
整理の方法
- どのようなトラブルが起きているか
- トラブルが発生したのはいつか
- 具体的にどのような被害にあったか
- トラブルを証明できる証拠
労働基準法違反に該当するかどうかが焦点となるため、証拠になる就業規則やタイムカード、給与明細をコピー、または写真で撮影しておくといいでしょう。
違反行為の申告
相談だけではアドバイスをもらって終わり、となってしまうかもしれませんが、申告手続きを行い、さらに証拠がしっかりあると動いてくれる可能性が高まります。
申告とは、違反行為を告発し対応を求める手続きを指します。
労働基準監督書に動いてなんらかの対応をしてほしいのであれば「実名・申告・直接訪問」がおすすめです。
匿名申告もできますが、実名での申告のほうが緊急性が高いと認識してもらえるでしょう。
公務員は労働基準監督署の管轄外
国や地方公共団体と個人の公務員の間には契約関係がないため、労働契約法や労働組合法が適用されません。
民間企業を基準にした法律で動く労働基準監督署や労働局では、契約関係がない公務員の相談には対応できないのです。
一般職の国家公務員は労働基準法も適用外なので、民間企業の労働者とは扱いが大きく異なります。(※一般職の地方公務員は労働基準法が適用される)
公務員に適用される法律
- 地方公務員法
- 国家公務員法
- 人事院規則
- 条例
公務員にも労働局とは異なる相談窓口があるので、トラブルに遭遇している方は必要に応じて利用してくださいね。
- 社会保険労務士
- 組合(※加入が必要)
- 国の機関
- 産業医
- 所属の相談員
- 人事院/地方自治体の人事院会
労働問題=「労働基準監督署に相談」が最適とは限らない!
日本には労働問題に関する相談機関が複数ありますが、全てが違う役割を持っています。
トラブルに巻き込まれてしまったら、どんな法律に関わる問題かを確認し、相談先を使い分けてください。
国の機関の利用時間は平日の9時~17時が多く、休みをとって訪問する方も多いでしょう。
勇気を出して訪問して「この機関では解決できない」「証拠がないと動けない」と門前払いされないよう、事前の準備をおすすめします。
今よりいい会社に転職しませんか?
転職活動は転職エージェントを活用した方が効率的です。
複数の転職支援サービスを併用すると希望通りの転職が実現しやすくなります。
リバティーワークスのおすすめは、転職成功実績No.1の『リクルートエージェント』と、業界・職種が幅広い『doda』です。
自分の市場価値がわかる『ミイダス』も利用すれば転職成功率はさらに上がります。
登録はスマホ一つで簡単!最短3分で完了!
転職エージェントのサポートは無料なので、まずは気軽に相談してみましょう。

転職成功実績No.1!非公開求人多数
幅広い業界・職種から希望条件にマッチする求人を紹介可能。
年代問わず転職決定者が多く、キャリアアップ・キャリアチェンジに強い。充実の面接対策も人気!

求人数20万件超!非公開求人多数!!
こだわり条件にマッチする求人を提供する国内最大級の求人情報・転職サイト。
特に営業職に強く、丁寧なサポートとアフターフォローに定評あり。大卒以上の26~35歳、関東、関西、東海の求職者向け。

求人の3割以上が年収1,000万円超。登録者のレジュメを見た企業やヘッドハンターから直接スカウトされるため採用率が高い。
必ず面談or面接できる「プラチナスカウト」では役員や社長面接確約も。キャリアアップを目指す人は外せないサービス。